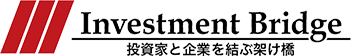ブリッジレポート:(2317)システナ 2026年3月期上期決算
 取締役社長 三浦 賢治 | 株式会社システナ(2317) |
 |
企業情報
市場 | 東証プライム市場 |
業種 | 情報・通信 |
代表取締役会長 | 逸見 愛親 |
取締役社長 | 三浦 賢治 |
所在地 | 東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング14階・16階 |
決算月 | 3月 |
HP |
株式情報
株価 | 発行済株式数(自己株式を控除) | 時価総額 | ROE(実) | 売買単位 | |
494円 | 357,455,827株 | 176,583百万円 | 24.0% | 100株 | |
DPS(予) | 配当利回り(予) | EPS(予) | PER(予) | BPS(実) | PBR(実) |
13.0円 | 2.6% | 28.98円 | 17.0倍 | 100.03円 | 4.9倍 |
*株価は11/19終値。26年3月期第2四半期決算短信より。発行済株式数は直近期末の発行済株式数から自己株式を控除。ROEは25年3月期実績。
連結業績推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS(円) | DPS(円) |
2022年3月(実) | 65,272 | 9,106 | 8,578 | 5,992 | 15.47 | -(*) |
2023年3月(実) | 74,526 | 9,844 | 9,955 | 7,317 | 18.89 | 8.00 |
2024年3月(実) | 76,940 | 9,713 | 9,942 | 7,232 | 18.67 | 10.00 |
2025年3月(実) | 83,621 | 12,067 | 11,855 | 8,480 | 23.17 | 12.00 |
2026年3月(予) | 90,200 | 14,500 | 14,900 | 10,360 | 28.98 | 13.00 |
・予想は会社予想。単位:百万円。
・2021年12月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の割合をもって株式分割を実施。2022年3月期のEPSは当該株式分割を考慮。EPS、DPSとも当該株式分割に伴う遡及調整は行っていない。
・2022年3月期のDPS(*)は中間10.00円、期末3.50円だが、当該株式分割の実施により単純合計ができないため表示していない。
(株)システナの2026年3月期上期決算の概要、2026年3月期の見通しなどをご報告致します。
目次
今回のポイント
1.会社概要
2.2026年3月期上期決算概要
3.2026年3月期業績予想
4.今後の注目点
<参考:コーポレート・ガバナンスについて>
今回のポイント
- 26/3期上期の売上高は前年同期比17.1%増の469億67百万円、営業利益は同36.2%増の75億93百万円。前期も業績のけん引役となった次世代モビリティ事業が依然好調を持続している他、デジタルインテグレーション事業、ビジネスソリューション事業もそれぞれ2桁増収を達成している。利益面では、次世代モビリティ事業を筆頭に主力事業が軒並み大幅増収を達成し、カバーした格好となっている。特にIT&DXサービス事業、ビジネスソリューション事業の増益率のモメンタムは第1四半期から加速。
- 26/3期通期の会社計画について、第1四半期決算と同時に上方修正していたが、それに続き中間決算と同時にさらに売上高を従来の896億円から902億円、営業利益は135億円から145億円、経常利益は135億円から149億円、親会社株主に帰属する当期純利益は94億円から103億60百万円にそれぞれ引き上げた。なお、配当見通しも上期6円、期末7円の年間13円と前期比1円の増額を見込む形に引き上げている。
- 次世代モビリティ事業に関して、国内完成車メーカーとメガサプライヤー側から、SDV開発の要望を受けて、同社が支援の幅を拡大している様子が説明会の中で明らかになるなど、先行き期待が高まった印象だ(取引先の面でも完成車メーカーをほぼ網羅してきている)。また、キーワードとして掲げていた「オールシステナ」の具体化の1つの姿とみられる、グループリソース活用による受注の取りこぼし抑止についても同事業で実践されているようであり、ポジティブ。なお、下期の同事業の見通しがやや保守的に見えるのは、同社が想定していたよりも大手完成車メーカーからの受注が後ろ倒しになったという事情があり、将来必ず訪れると同社が考えている受注のピークに向けて、先行して構築部隊への投資と体制整備を進めている影響とのことである。
1.会社概要
2010年4月1日に(株)システムプロが、持分法適用会社であったカテナ(株)を吸収合併して誕生。旧(株)システムプロのモバイル端末の設計・開発・検証に係る技術・ノウハウとオープン系技術、旧カテナ(株)の金融分野の業務知識及び基盤系技術を融合した事業展開により新たな領域の開拓を進めている。連結子会社8社及び持分法適用会社4社と共にグループを形成している。
【経営目標 - 日本を代表するIT企業となり、日本経済を底辺から支える! 】
経営目標実現のために、「破壊と創造」、「安定と成長」、「保守と革新」という、相反する課題をバランス良くコントロールし、常に振り子の中心点に経営の軸足を置いた、バランス経営を基本方針としている。
【目標とする経営指標】
目標とする経営指標として、安定した高配当、高い株主資本利益率、高い売上高営業利益率を掲げており、その実現に向け、経営の基本方針に則り、高収益体質を目指していく考え。
1-1 事業内容
2025年3月期から、「ソリューションデザイン事業」「次世代モビリティ事業」「フレームワークデザイン事業」「IT&DXサービス事業」「ビジネスソリューション事業」「DX&ストック型ビジネス事業」「その他事業」の7セグメントとしている。ただし、2026年3月期からは「ソリューションデザイン事業」から一部事業を移管して「プロジェクトマネジメントデザイン事業」へ、「フレームワークデザイン事業」は「デジタルインテグレーション事業」へとセグメント名称を変更している。
◆次世代モビリティ事業
完成車メーカーやサプライヤー向けを中心に、自動車業界へのエンジニアリングおよびMaaSなどの自社サービスの提供を主な業務とする。同社の携帯電話/スマートフォン開発におけるAndorid/iOSなどのオープンプラットフォーム開発の長年積み上げた実績、つまりモバイル開発で進めてきたアジャイル手法やアプリケーションフレームワークを採用した開発は、SDV開発に必要なものとなっており、ソフトウェアTier1として様々な完成車メーカーやメガサプライヤーに技術力を提供している。
◆プロジェクトマネジメントデザイン事業
各種プロダクト製品、通信事業者サービスの企画・設計・開発・検証支援の他、ネットビジネス、業務用アプリ、Webサービス、社会インフラ関連システム、IoT、人工知能、ロボット関連サービスの企画・設計・開発・検証支援を手掛ける。通信キャリア、通信機器メーカー、インターネットビジネス企業を主要顧客とし、長年にわたるモバイル端末の開発で培った豊富なノウハウと実績を基に、電力・防災・航空・交通などの社会インフラ、情報家電やホームセキュリティ、スマートデバイスやWebサービスなど、様々な分野で成長中である。あらゆる分野で企画から開発・検証、ITコンサルティングやITサービスまで提供できるトータルソリューションが強み。
◆デジタルインテグレーション事業
金融系(損保・生保・銀行)、産業系、公共系、その他の基幹システムの開発の他、基盤系システムの開発を手掛ける。高い信頼性を求められる金融系システム開発において、半世紀以上にわたり蓄積してきたノウハウ・経験と実績を武器に、金融以外の業種においてもソリューションを提供する。昨今では、基幹系システムの開発から、顧客のビジネス変革を支えるDX推進へ業務範囲を広げている。中央省庁案件の継続的な獲得も強み。
◆IT&DXサービス事業
ITプロジェクト推進・PMO、DX支援、システム構築から運用、データ入力、大量出力、ソフトウェアテスト・DX検証などのITアウトソーシングサービスの提供を行う。リソースをコア業務へ集中する企業の動きが活発化するなか、個々のサービスを提供するだけではなく、ALLシステナによるトータル・ソリューション・サービスの提供で、IT戦略の実現サポートが可能な点が強み。
◆ビジネスソリューション事業
サーバー、パソコン、周辺機器、ソフトウェアなどIT関連商品の企業向け販売。基盤構築、仮想化などIT機器に関わるサービスの提供やRPAソリューションの提供を行う。
◆DX&ストック型ビジネス事業
自社サービス「Canbus.」、「Cloudstep」、「Web Shelter」の提供。さらに「Google Workspace」、「Microsoft 365」等クラウド型サービスの提供、導入支援。DX推進を支援するPMOおよびディレクションサービスとしての「Canbus.Lab」の提供を行う。
◆その他
自動車メーカーの車載コクピットにおける情報表示関連のソフトウェア開発、スタートアップ活用の事業コンセプトPoC開発、ノーコードツールCanbus.による企業のDX推進。また、IoM(IoT/M2M)5Gゲートウェイ、LTEルーター、DCM端末およびIoM向けアンテナ、5G・LTEフェムト基地局の開発と製造、販売。スマホ/PC向けソーシャルゲームの企画・開発・運営、アプリ/システム開発受託を手掛ける。
1-2 グループ会社

(同社資料より)
1-3 中期経営計画(2026年3月期~2028年3月期)
同社では、新たに2028年3月期に向けて中期3カ年計画を策定した。中計最終年度である2028年3月期の業績は売上高1,027億円、営業利益160億円、営業利益率15.6%を目標としている。この目標の達成に向けて、営業強化、ストック型ビジネスの拡充、成長分野への集中投資、既存事業のスクラップアンドビルドを行うとともに、人材への投資を通じた生産性向上に取り組んでいく方針である。
■経営方針の詳細
中期3カ年計画達成のため、事業セグメントの枠にとらわれることなく、今まで以上に本部間連携を強化し、「オールシステナ」体制で、生産性向上と、より付加価値の高いビジネスの拡大に注力する。そのなかで、成長が鈍化するソリューションデザイン事業においては、引き続き各分野を深耕することで事業ドメインの再構築を行い、当事業が得意とする従来型の仕様策定ならびに設計工程に、各業界の専門知識を持つスペシャリストを採用することで、全工程のプロジェクトマネジメントと仕様設計を一体化したIT課題解決支援へと事業領域を拡大していく。
また、業界を問わず人材不足が深刻化しているなか、同社グループにおいても、優秀な人材確保が急務であり、引き続き、従業員の待遇改善や更なる賃金の引き上げを行い、特に技術力の高いエンジニアの採用、協力会社の発掘や収益確保のためのストック型ビジネスへの投資を積極的に取り組んでいく。さらに、生産性の向上に加え、ソフトウェア開発ビジネス等におけるDX推進を支援するコンサル業務やPMO案件といった付加価値の高いビジネスの拡大に注力し、コスト増加分を早期に価格転嫁できるよう推進していく。
■重視する経営指標と2028年3月期の目標
| 2025年3月期実績 | 2026年3月期予想 | 2027年3月期予想 | 2028年3月期予想 |
売上高(百万円) | 83,621 | 90,200 | 94,700 | 102,760 |
営業利益(百万円) | 12,067 | 14,500 | 13,800 | 16,000 |
営業利益率 | 14.4% | 16.1% | 14.6% | 15.6% |
2.2026年3月期上期決算概要
2-1 連結業績
| 25/3期上期 | 構成比 | 26/3期上期 | 構成比 | 前年同期比 |
売上高 | 40,092 | 100.0% | 46,967 | 100.0% | +17.1% |
売上総利益 | 9,952 | 24.8% | 12,205 | 26.0% | +22.6% |
販管費 | 4,378 | 10.9% | 4,611 | 9.8% | +5.3% |
営業利益 | 5,573 | 13.9% | 7,593 | 16.2% | +36.2% |
経常利益 | 5,410 | 13.5% | 7,927 | 16.9% | +46.5% |
親会社株主帰属利益 | 3,726 | 9.3% | 5,502 | 11.7% | +47.7% |
*単位:百万円
前年同期比17.1%の増収、同36.2%の営業増益
日本経済は、春季賃上げの効果に段階的な浸透による個人消費の持ち直しや、堅調なインバウンド需要に支えられ、緩やかな回復基調を維持した。一方で、依然として歴史的な円安水準が継続していることに加え、中東情勢の緊迫化など地政学リスクを背景とした原油・資源価格の変動が、輸入物価を通じて企業収益や家計の実質購買力を圧迫する懸念も高まっている。また、根強いインフレを背景とした米国をはじめとする主要国での金融政策の動向や、世界的なサプライチェーンの再編に向けた動きなど、先行きは依然として不透明な状況が続いている。このようななか、同社グループは、外部環境の変化に迅速に対応すべく、経営資源の再配置や生産性の向上に努めた。収益基盤の強化に向けては、安定的な収益が見込めるストック型ビジネスに引き続き注力。加えて、ソフトウェア開発ビジネスにおいては、生成AIの活用、企業のDX推進支援、高度なプロジェクト管理能力が求められるPMO案件など、付加価値の高い領域の拡大を積極的に推進した。人材育成については、継続的なOJTを通じた教育によって組織力が底上げされ、適材適所への配置最適化が進み、更に攻勢に転じる体制が整った。
売上高は前年同期比17.1%増の469億67百万円。前期に続き、今期も「報告セグメント」の組替と一部名称の変更を実施している。前期も業績のけん引役となった次世代モビリティ事業が依然好調を持続している他、デジタルインテグレーション事業、ビジネスソリューション事業もそれぞれ2桁増収を達成している。
利益面では、DX&ストック型ビジネス事業とその他事業が苦戦したものの、次世代モビリティ事業を筆頭に主力事業が軒並み大幅増収を達成し、カバーした格好となっている。特にIT&DXサービス事業、ビジネスソリューション事業の増益率のモメンタムは第1四半期から加速。この結果、全体としては営業利益ベースで同36.2%増の75億93百万円での着地となった。なお、売上高総利益率は26.0%と前年同期から1.2pt改善。売上高販管費率は同1.1pt低下の9.8%となった。
2-2 セグメント別動向
| 25/3期上期 | 構成比・利益率 | 26/3期上期 | 構成比・利益率 | 前年同期比 |
次世代モビリティ | 2,447 | 6.1% | 3,606 | 7.7% | 47.3% |
プロジェクトマネジメントデザイン | 7,756 | 19.3% | 7,834 | 16.7% | 1.0% |
デジタルインテグレーション | 4,201 | 10.5% | 4,938 | 10.5% | 17.5% |
IT&DXサービス | 10,073 | 25.1% | 10,917 | 23.2% | 8.4% |
ビジネスソリューション | 13,878 | 34.6% | 18,066 | 38.5% | 30.2% |
DX&ストック型ビジネス | 1,494 | 3.7% | 1,609 | 3.4% | 7.7% |
その他 | 428 | 1.1% | 328 | 0.7% | -23.4% |
調整額 | -188 | -0.5% | -334 | -0.7% | - |
連結売上高 | 40,092 | 100.0% | 46,967 | 100.0% | 17.1% |
次世代モビリティ | 893 | 36.5% | 1,511 | 41.9% | 69.1% |
プロジェクトマネジメントデザイン | 1,178 | 15.2% | 1,698 | 21.7% | 44.2% |
デジタルインテグレーション | 875 | 20.8% | 1,205 | 24.4% | 37.7% |
IT&DXサービス | 1,302 | 12.9% | 1,510 | 13.8% | 15.9% |
ビジネスソリューション | 1,092 | 7.9% | 1,566 | 8.7% | 43.4% |
DX&ストック型ビジネス | 224 | 15.0% | 134 | 8.3% | -40.2% |
その他 | 6 | 1.4% | -32 | - | - |
連結営業利益 | 5,573 | 13.9% | 7,593 | 16.2% | 36.2% |
*単位:百万円
次世代モビリティ事業-売上高36億6百万円(前年同期比47.3%増)、営業利益15億11百万円(同69.1%増)
既存の主要顧客に加え、新たな国内の主要完成車メーカーとの直接取引が始まった。また、米国子会社による日本の完成車メーカーとの直接取引も開始し、北米市場における案件創出基盤の強化につながっている。現在、自動車業界ではSDV(Software Defined Vehicle)を前提とした設計・開発への移行が進んでおり、コックピット領域(IVI*1/HUD*2/CDC*3)からバックエンド(HVAC*4/ADAS*5)に至るまで、ソフトウェア開発の需要が拡大している。この潮流を捉え、同事業はモバイル領域で培ったUXデザインやアジャイル開発の強みを車載領域に応用・展開することで、受注と稼働の安定化を実現した。さらに、完成車メーカーによる新たなモビリティ開発に企画・要件定義といった最上流段階から参画するとともに、OEMの開発プロセスがSDV前提へ移行するのに合わせ、上流工程から統合工程まで一貫して連続支援できる体制を構築した。引き続きモビリティソフトウェアのTier1相当の役割を見据え、体制・プロセスの強化と国内外の連携を並行して進め、同事業のサービス提供範囲の拡大を図る方針だ。
*1 IVI : In-Vehicle Infotainment (情報・娯楽の両要素の提供を実現する一体化された車載システム)
*2 HUD : Head-Up Display(人間の視野の中に周囲の光景に溶け込むよう重ね合せ情報を投影させる表示装置)
*3 CDC : Cockpit Domain Controller (コクピットの様々な機能を一つの電子制御ユニットに集約したもの)
*4 HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning(自動車の空調システム全体を指す言葉)
*5 ADAS: Advanced Driver-Assistance Systems(自動車に搭載されたセンサーやカメラなどを活用し、運転中の事故のリスクを低減したり、運転の負担を軽減したりする機能)
プロジェクトマネジメントデザイン事業-売上高78億34百万円(前年同期比1.0%増)、営業利益16億98百万円(同44.2%増)
旧ソリューションデザイン事業から一部事業を移管した同セグメントにおいては、注力分野である次世代通信およびAI領域において、プロジェクト支援体制を拡大し、あわせてプロジェクトの実行体制の強化に向けたリソースの再配置を実施。通信分野では、新規サービス開発支援に加え、システムインフラ基盤の刷新における要件定義、進行管理、技術調査から移行支援まで一貫して実施した。AI分野では、生成AIを活用したプラットフォーム再構築や新サービス立ち上げにおけるマネジメント支援案件が増加したほか、AIの適用検討やPoC(概念実証)といった上流工程への関与も拡大した。加えて、モビリティ分野でも、PMO支援を開始したことが受注増に貢献した。
デジタルインテグレーション事業-売上高49億38百万円(前年同期比17.5%増)、営業利益12億5百万円(同37.7%増)
旧フレームワークデザイン事業から名称変更した同事業においては、金融分野では、特に保険とネットバンク領域での受注拡大が続いており、事業の拡大を牽引している。公共分野では、マイナンバー制度を背景とした中央省庁関連案件が引き続き堅調に推移し、システム更改、インフラ構築、運用保守といった広範な領域で事業を拡大している。地方自治体におけるDX推進の動きも活発化しており、公共分野は引き続き同事業の主要な柱の一つとなっている。特に足元の地方自治体向けでは教育関連、事務改善をテーマにしたDX案件が増加。法人分野では、ローコード開発ツールを活用した迅速な技術支援サービスと、顧客のDX推進を加速するシステム開発案件の獲得に注力しており、システム企画から開発後の運用保守まで一貫したサポートは、顧客からも高評価を得ており、競争力強化に繋がっている。さらに、生成AIの活用においては、業務効率化だけでなく、開発生産性の向上を目指したAI駆動開発のニーズも高まっている。同事業では、人材育成への積極的な投資を含め、技術力の強化を一層推進している状況だ。
IT&DXサービス事業-売上高109億17百万円(前年同期比8.4%増)、営業利益15億10百万円(同15.9%増)
各企業のデジタルビジネス化に向けたIT投資意欲の高まりを背景に、幅広い業界でシステム更改や導入の引き合いが続いているほか、近年は「業務プロセスの最適化(標準化・自動化)」や「各種ツール導入後の利活用・運用推進」といった需要が特に高まっている。このような市況において、顧客のIT投資計画を把握した上で、ツール導入支援、導入後の利活用推進、業務プロセス再構築といった「伴走型PMOサービス」の更なる拡大に注力した。DX検証サービス事業においては、ネットビジネス/ゲーム領域での知見を活かし、エンタープライズ領域顧客へのシフトを進めている。人材配置の適正化と即戦力人材の調達を強化し、既存顧客の深掘りと新規顧客の開拓を推進。また、特例子会社である東京都ビジネスサービスでは、障がい者一人ひとりの能力やキャリア形成を支援する制度構築を進めた。これにより一段と適材適所化が実現し、BPO業務を中心に幅広いサービス案件の受注に繋がった。
ビジネスソリューション事業-売上高180億66百万円(前年同期比30.2%増)、営業利益15億66百万円(同43.4%増)
円安、原材料や物価の高騰など先行き不透明感はあるものの、DXやAIによるデジタル化や生産性の向上、コスト削減、競争力強化に向けた案件が活性化。具体的には、クラウドへのリフト&シフト案件をはじめ、クラウドの利活用案件の増大、更にはマネージドサービスの拡大と、クラウド関連のシステムインテグレーションビジネスを数多く受注した。また、RPAやデータ連携ツールを活用した企業のデジタル化に向けたシステム開発、保守運用案件、セキュリティサービスやサポートサービスについても多くの引き合いがあり、受注が増加。さらにはクライアントビジネスに関しても、Windows10のサポート終了(2025年10月)に伴うリプレース案件が大幅に増加した。
DX&ストック型ビジネス事業-売上高16億9百万円(前年同期比7.7%増)、営業利益1億34百万円(同40.2%減)
特に大手企業からの「Canbus.」導入に関する引き合いが好調に推移しており、この需要に対応すべく、今後も「Canbus.」の機能強化、並びに開発・サポート体制の強化を一層加速させていく方針である。また、新たな取り組みとして医療業界向けパッケージの受注を開始し、「Canbus.」シリーズのソリューション提供範囲を拡大した。引き続き、モビリティ業界をはじめとする他分野への展開やアライアンスを含む事業連携を深め、ストック型ビジネスの基盤強化に注力する。ただし、業務改善の支援をする中で、AIを活用した改善提案の要望が増加傾向にあり、AIを用いた製品開発の投資を増大。加えて、販路拡大のために、販売パートナーの開拓および展示会などのイベント企画を強化するなど、更なるストックビジネスの拡大に向けた積極投資を継続している影響で利益面では苦戦している。
その他事業-売上高3億28百万円(前年同期比23.4%減)、営業損失32百万円(前年同期は6百万円の利益)
スマホゲーム「競馬伝説PRIDE」においてリリース3周年を記念したキャンペーンとして新たな強化要素「併せ特訓」を実装し、ゲーム内の動向がより活性化するよう施策をうった。受託/SES開発では主にゲーム系開発のPMO支援、全体の工数管理、運用保守開発を行なっている。今後はこれまでのゲーム系開発で培ったノウハウをゲーミフィケーション領域等へ展開する取組を推進していく方針である。
2-3 財政状態
◎BS
| 25年3月 | 25年9月 |
| 25年3月 | 25年9月 |
現預金 | 21,860 | 24,656 | 仕入債務 | 9,063 | 8,049 |
売上債権 | 18,605 | 18,187 | 未払金・未払費用 | 2,530 | 2,532 |
商品 | 2,053 | 1,231 | 未払法人税 | 2,167 | 2,580 |
流動資産 | 44,184 | 45,935 | 賞与引当金 | 2,068 | 1,810 |
有形固定資産 | 1,321 | 1,417 | 有利子負債 | 1,550 | 1,550 |
無形固定資産 | 169 | 152 | 負債 | 18,812 | 17,928 |
投資その他 | 6,087 | 6,651 | 純資産 | 32,950 | 36,228 |
固定資産 | 7,578 | 8,221 | 負債・純資産合計 | 51,762 | 54,157 |
*単位:百万円。売上債権は受取手形と売掛金、契約資産の合計。

*株式会社インベストメントブリッジが開示資料を基に作成。
25年9月末の総資産は前期末との比較で23億95百万円増の541億57百万円。資産サイドでは、流動資産において受取手形、売掛金及び契約資産、商品が減少。負債は、同8億84百万円減の179億28百万円。これは主に買掛金、賞与引当金の減少が背景である。純資産は、同32億78百万円増の362億28百万円。自己資本比率は66.0%と前期末比3.3ポイント上昇。
キャッシュ・フロー(CF)
| 25/3期上期 | 26/3期上期 | 前年同期比 | |
営業キャッシュ・フロー(A) | 3,457 | 5,922 | 2,465 | 71.3% |
投資キャッシュ・フロー(B) | -305 | -287 | 18 | - |
フリー・キャッシュ・フロー(A+B) | 3,152 | 5,635 | 2,483 | 78.8% |
財務キャッシュ・フロー | -11,541 | -2,157 | 9,384 | - |
現金及び現金同等物期末残高 | 21,681 | 24,942 | 3,261 | 15.0% |
* 単位:百万円
CFの面では、投資CFは概ね同水準だった一方、営業CFが前年同期比で大幅に増加したことにより、フリーCFも結果的に拡大した。また、財務CFはマイナス幅が縮小した。これは、主に前年同期にあった自己株式の取得の剥落によるもの。以上の結果により、現金及び現金同等物期末残高は前年同期比15.0%増加した。
2-4 最近のトピックス
(1)「第8回 [名古屋]オートモーティブ ワールド -クルマの先端技術展-」にスーパーマイクロ社、日本AMD社と共同出展
2025年10月29日(水)~31日(金)の3日間、ポートメッセなごやにおいて開催された、「第8回[名古屋]オートモーティブ ワールド -クルマの先端技術展-」にスーパーマイクロ株式会社(以下「スーパーマイクロ」)、日本AMD株式会社(以下「AMD」)と共同出展した。
近年、車載開発においてSDVへの移行が進み、ソフトウェアの重要性が飛躍的に高まっている。このトレンドに対応し、開発の幅を広げ、より高度なソリューションを提供するため、今回の3社共同での展示会出展にいたった。今回の展示会では、同社からはAIを活用した車載開発効率化のサービスを、スーパーマイクロ及びAMDからはOSを最大限に活用するための高性能コンピューティングのサーバーを展示している。それぞれの分野における最新技術を持ち寄ることで、ソフトウェアとハードウェアが高度に連携した次世代の車載システム開発を強力に推進し、顧客へ革新的で幅広い開発の選択肢提案を目指す。
(2)「Canbus.」を第5回デジタル化・DX推進展(大阪会場)に出展
2025年10月30日(木)・10月31日(金)の2日間、インテックス大阪で開催された「デジタル化・DX推進展」内の専門展示会「AI活用支援EXPO」に出展した。デジタル化・DX推進展は、デジタル化を推進したい自治体と、DXの推進により営業組織や経営基盤の強化、バックオフィスの業務効率化、働き方改革を実現したい企業に向けたBtoB展示会である。企業のDX推進をAI活用によって支援する「AI活用支援EXPO」をはじめ、10の専門展で構成されており、デジタル技術を活用したソリューションを展示している。
◆出展の見どころ
多くの企業がDX推進でぶつかる「DXを進めたいが、何をすべきか分からない」「IT人材がいない」「ツールを入れたが社内に浸透しない」といった『壁』。根本原因は、現状の課題に気づけていないことにある。この壁を突破するため、同社はノーコードプラットフォーム「Canbus.」とコンサルティング支援を組み合わせたソリューションと内製化支援で、顧客自身がDXを推進できる「自走できる組織」づくりを実現する。今回の出展では、製造業・自動車業界にフォーカスした「Canbus.」とAIを組み合わせた多様なソリューションを紹介した。
(3)NTTデータの新パートナー制度「コアビジネスパートナー」に認定
株式会社NTTデータ(本社:東京都江東区、代表取締役社長:鈴木 正範、以下 NTTデータ)より、新パートナー制度における「コアビジネスパートナー」に認定された。「コアビジネスパートナー」は、NTTデータが事業のさらなる展開に向けて、継続的な協力を期待する国内の重要パートナー企業を認定する制度である。この度、認定されたのは10社で、そのうちの1社となる。引き続き、これまで培ってきた技術力に一層磨きをかけるとともに、NTTデータとのパートナーシップをより強固なものとしていく方針である。
(4)SB C&S社とSaaS製品の販売拡大に向けて協業強化
急速に成長するSaaS(Software as a Service)市場への参入を加速させるため、SB C&S株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO:草川 和哉、以下「SB C&S」)とこれまで築いてきた協業の基盤を生かし、連携体制をより強化する。
ITディストリビューターであるSB C&Sは、SaaS市場の拡大に対応するためSaaS専任チーム「CloudService Concierge(クラウドサービスコンシェルジュ)」を発足し、SaaS製品に関するマーケティングや販売支援を推進している。また、SB C&Sが提供するサブスクリプション契約・更新管理のための販売パートナー向けプラットフォーム「ClouDX(クラウディーエックス)」では、製品ごとに異なる契約形態であるSaaS製品を一括で管理できる。今後、同社が持つ販売力とSB C&SのSaaSビジネスで培ったノウハウを組み合わせ、連携を深めることでSaaS製品の提案から導入までを包括的にサポートする支援体制を強化していく狙いだ。
3.2026年3月期業績予想
3-1 連結業績
| 25/3期 実績 | 構成比 | 26/3期 予想 | 構成比 | 前期比 |
売上高 | 83,621 | 100.0% | 90,200 | 100.0% | +7.9% |
営業利益 | 12,067 | 14.4% | 14,500 | 16.1% | +20.2% |
経常利益 | 11,855 | 14.2% | 14,900 | 16.5% | +25.7% |
親会社株主帰属利益 | 8,480 | 10.1% | 10,360 | 11.5% | +22.2% |
*単位:百万円
通期予想を再度上方修正。前期比7.9%の増収、同20.2%の営業増益予想
第1四半期決算と同時に26/3期通期の会社計画を上方修正していたが、それに続き中間決算と同時にさらに売上高を従来の896億円から902億円、営業利益は135億円から145億円、経常利益は135億円から149億円、親会社株主に帰属する当期純利益は94億円から103億60百万円にそれぞれ引き上げた。事業セグメントの枠にとらわれることなく、今まで以上に本部間連携を強化し「オールシステナ」体制で、生産性向上と、より付加価値の高いビジネスの拡大に注力し、新たに掲げた3カ年の中期経営計画の推進を目指す。経営資源の再配置をダイナミックに実行したことで、成長事業へ経営資源をシフトすることが可能となり、契約単価上昇を実現。それに加えて、高付加価値案件の受注増加も寄与して上方修正に繋がった。
また、業界を問わず人材不足が深刻化しているなか、同社グループにおいても、優秀な人材確保が急務であり、引き続き、従業員の待遇改善や更なる賃金の引き上げなどに取り組む一方、採用方針については、経験者採用に軸足を移すことで教育・研修の効率化と採用ミスマッチの低減を図っていく方向に変化する。売上高営業利益率は14.3%と前期とほぼ同水準の計画だったが、上方修正に伴い16.1%と向上した。
なお、配当見通しも上期6円、期末7円の年間13円と前期比1円の増額を見込む形に引き上げている。
3-2 セグメント別の取組み
(1)次世代モビリティ事業
方針:自動車のSDV(Software Defined Vehicle)化に伴い、モバイルとモビリティの経験を活かし、ソフトウェアTier1として新たな事業展開を目指す
1.モバイル技術を活かしたSDV開発へ注力
・モバイル開発で磨いてきたUI/UXや設計・開発のノウハウを活かし、車載コクピット領域(IVI・HUD・CDCなど)のソフトウェア開発に深く関与し、高い付加価値を提供する。
2.通信領域での知見を活かした車載通信分野への戦略的注力
・これまで通信事業者向けに展開してきたネットワーク制御・プロトコルスタック・セキュリティ実装の知見を、コネクティビティ機能の車載通信領域に応用する。
3. SDV時代における通信技術とモバイル開発を融合し、ブランド体験の高度化を支援
・SDV時代のクルマに求められる“つながる体験”を実現するため、通信とモバイル技術を融合したUX設計支援を推進。スマホ連携やデジタルキー、ポータル統合など、ブランドごとの一貫した体験設計を完成車メーカーにおいて支援。機能提供にとどまらず、「選ばれる体験」をつくるためのプロトタイプ・評価設計まで一気通貫で支援。
(2)プロジェクトマネジメントデザイン事業
方針:自社開発力を活かした対応を展開し、実行型プロジェクトマネジメントで付加価値の高い事業分野の創出を目指す
1.成長分野への積極展開
・成長分野への選択と集中を進め、次世代通信、AI、モビリティの各領域におけるプロジェクトマネジメントに注力。
2.組織力強化
・開発力とマネジメント力を掛け合わせた、当事業の強みである「実行型プロジェクトマネジメント」を強みに、計画策定や管理に留まらず、進捗・品質・課題対応を一体で推進していくための人材育成と採用に投資する。
3. 次世代モビリティ事業との連携
・完成車メーカーにおけるSDV関連の大規模プロジェクトや開発・評価工程を担うPM、現場の業務改善を担うDX関連PMなど、次世代モビリティ事業との連携により相乗効果で支援領域を拡充する。
(3)デジタルインテグレーション事業
方針:業務システム開発におけるDXニーズを捉え、顧客の成長を支えるインテグレーションサービスを提供する
1.徹底した顧客基盤の強化
・DXの本格化に向けた顧客ニーズを捉えて、継続的なビジネス拡大と、顧客基盤の強化を図る。
2.高付加価値ビジネスへのシフト
・生成AIをフル活用した開発生産性の向上を実現し、システム開発における競争力を強化。
・DX推進を支える、「ローコード開発」、「DXソリューション」に対応したサービスを拡充。
3.ビジネスモデルの変革
・システム開発ノウハウをアセット化し、同社から価値を提供する能動型ビジネスモデルへ転換を進める。
(4)IT&DXサービス事業
方針:顧客のニーズに対して提案するだけではなく、顧客の潜在的な課題を可視化(アセスメント)した上で、包括的なサービスを強化
1.顧客のデジタルビジネスに向けたサービスの提供に注力
・各種ツールの導入支援や導入後の利活用、業務プロセスの再構築といった伴走型のPMOサービスの更なる拡大。
2.オファリングサービスの推進・強化
・サービス・プロダクト・ノウハウを組み合わせた最適なサービスメニューを提案し、顧客の企業価値向上をサポート。
3.リスクマネジメントサービスの拡大
・顧客のサービスリスクを把握予測し、解決のためのサービスをコンサル~テストの全工程分野でサービス業務を拡充。
(5)ビジネスソリューション事業
方針:モノビジネスからサービスビジネスへと軸足をシフト
1.ソリューション領域拡大への投資
・サービスメニューの拡充とプロフィット部門への営業展開。
2.ハイブリッド環境への取り組み強化
・ハイブリッド環境への対応強化とクラウドメーカーとのアライアンス強化。
・Win10EOL(End Of Life)後のインフラビジネスの強化。
3.DX関連サービス拡大
システム開発他、マルチクラウド環境でのアプリケーションの再構築事業を強化。
4.サービスの拡範による収益力の強化
・ ALL Systenaの全てのサービスをワンストップで提供。
(6)DX&ストック型ビジネス事業
方針:『Canbus.』を中心とした自社サービスへの積極的な先行投資を行い、DX分野への展開を目指す
1. Canbus.の業種特化型パッケージ企画
・製造業/医療業界向けのパッケージ提案を強化し、導入時のインテグレーション支援もセットで拡大。
2.Canbus.の認知度向上
・イベント出展、パートナーとの共同イベント、SNSマーケティングなど様々な広告宣伝活動を行う。
3. DX/AIの伴走支援の強化
・システム部門やDX推進部門の支援をはじめ、AI活用のユースケースの選定およびPoC支援から全社導入までの一連の伴走サービスを展開。
4.今後の注目点
次世代モビリティ事業に関して、国内完成車メーカーとメガサプライヤー側から、SDV開発の要望を受けて、同社が支援の幅を拡大している様子が説明会の中で明らかになるなど、先行き期待が高まった印象だ(取引先の面でも完成車メーカーをほぼ網羅してきている)。また、キーワードとして掲げていた「オールシステナ」の具体化の1つの姿とみられる、グループリソース活用による受注の取りこぼし抑止についても同事業で実践されているようであり、ポジティブ。なお、下期の同事業の見通しがやや保守的に見えるのは、同社が想定していたよりも大手完成車メーカーからの受注が後ろ倒しになったという事情があり、将来必ず訪れると同社が考えている受注のピークに向けて、先行して構築部隊への投資と体制整備を進めている影響とのことである。組織再編(改革)は中間期でほぼ完成との説明もあったことから、引き続き全事業ともこのままモメンタムを維持・加速していけるか注目。
<参考:コーポレート・ガバナンスについて>
◎組織形態及び取締役、監査役の構成
組織形態 | 監査役設置会社 |
取締役 | 11名、うち社外4名 |
監査役 | 4名、うち社外4名 |
◎コーポレート・ガバナンス報告書(更新日:2025年6月20日)
基本的な考え方
当社は、激しい経営環境の変化に対応し、経営の効率性を高めるために迅速な意思決定によるスピード経営を推し進め、永続的な事業発展と株主価値の増大および株主への継続的な利益還元を行っていくと同時に、株主、顧客、取引先、従業員および地域社会などのステークホルダー(利害関係者)との利害を調和させ、全体としての利益を最大化することを目指し、かつ、経営の健全性確保およびコンプライアンス(法令遵守)の徹底に努めるためにコーポレート・ガバナンスを強化させていきたいと考えております。このため、外部専門家(監査法人、主幹事証券会社、弁護士、社会保険労務士、司法書士等)やステークホルダーからの指摘や提言を真摯に受け止め、経営の公平性、透明性に関して更なる充実を図る所存であり、持ち前の当社の機動性を活かし、会社規模に応じた体制を構築し、株主などのステークホルダーを絶えず意識した上場企業として一層の自己改革を図り、コーポレート・ガバナンスの強化と適時適切な情報開示に努める所存であります。
<実施しない主な原則とその理由>
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
【補充原則2-4①中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、性別・年齢・人種・国籍・新卒中途などの属性に関わらず管理職への登用を行っており、実力に応じた処遇と適材適所を方針としています。詳細は以下のホームページをご覧ください。
「中核人材の多様性確保の考え方」https://www.systena.co.jp/sustainability/esg_society/
【原則3-1.情報開示の充実】
【補充原則3-1③サステナビリティについての取組み】
当社のサステナビリティに関する取組みは以下のホームページをご覧ください。なお、プライム市場上場会社のみに課されているTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示についての当社の対応をご説明いたします。当社はITサービスの提供を社業としており、物品の製造など環境負荷の高い事業は行っておりませんので、現在のところ、気候変動問題が当社事業に重大な影響を及ぼすことは想定されません。しかしながら、地球環境が人類共通の財産であり未来からの大切な預かりものであるという認識に基づき、2004年からISO140001の認証を取得し、資源利用の低減とごみの排出削減に努めております。また、気候変動にかかる企業各社の対応のうちIT化にかかる部分はすべて当社の事業領域であり、当社の収益拡大は、お客様の業務効率化に貢献し、資源利用の低減とごみの排出削減へとつながり、地球環境保全に貢献します。このため、当社の成長が気候変動を抑えることにつながると考えております。なお、当社は2025年3月期から温室効果ガス排出量のScope1、2、3別計測への取り組みを開始し、2026年3月期末までに温室効果ガスの排出削減目標を立てた活動を開始していく予定です。その過程においてTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示を必要に応じて検討してまいります。なお、当社の環境に関する取り組みは、以下のホームページをご覧ください。
「当社のサステナビリティに関する取組み」
https://www.systena.co.jp/sustainability/
「当社の環境に関する取組み」
https://www.systena.co.jp/sustainability/esg_environment.html
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者の計画】
当社は、指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名(後継者計画を含む。)・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化しておりますが、現在のところ後継者計画は策定しておりません。今後、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-3③ 最高経営責任者を解任するための客観性、適時性、透明性のある手続きの確立】
当社は創業者でありオーナー経営者でもある代表取締役が最高経営責任者として経営の大きな方向性の舵取り行い、業績等の適切な評価をもって社内を統率する体制を取っております。加えて代表取締役はいずれも独立役員の要件を満たした8名(社外取締役4名と社外監査役4名)の社外役員から牽制を受ける体制になっており、代表取締役を解任するような事態が生じた場合は独立役員からの提言をもとに取締役会にて議論のうえ、決定することで対処できると考えております。このため、現在のところ取締役会は最高経営責任者を解任するための客観性、適時性、透明性のある手続きの確立を行っておりません。今後、必要に応じて検討してまいります。
<開示している主な原則>
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、原則、政策保有株式として上場株式を保有しない方針であります。しかし、企業価値向上に向けて戦略上重要な協業および取引関係の維持発展等が認められる場合は、取締役会において個別銘柄ごとに保有目的、保有意義等を検証し、保有の適否を判断しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念、経営戦略、経営計画
当社は、経営理念や経営戦略、中期経営計画を策定し、開示しております。詳細は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
「経営理念・行動基準」
https://www.systena.co.jp/about/idea.html
「経営目標と経営の基本方針」
https://www.systena.co.jp/ir/management/business_plan.html
「中期経営計画」
https://www.systena.co.jp/ir/management/business_plan.html
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「I.1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書「II.1.【取締役報酬関係】」に記載しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者の選任・指名に当たっては、指名・報酬委員会の委員長が実績・人格・見識・能力等を総合的に判断した上で指名・報酬委員会に提案し、指名・報酬委員会において、取締役会全体として的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監督ができる人員構成となるよう適任者を選び、取締役会にその意見を提示しております。取締役、監査役または執行役員を解任すべき事情が生じた場合には、取締役会が審議を行い、取締役、監査役に関してはその解任案を、執行役員に関してはその解任をそれぞれ決定することとしております。なお、取締役、監査役の解任は会社法等の規定に従って行います。また、監査役候補者の選任・指名に当たっては、代表取締役が、実績・人格・見識・能力等を総合的に判断した上で取締役会に提案し、取締役会において財務・会計または法律に関する知見や経営監視の経験等のバランスを考慮し、候補者を選んでおります。なお、監査役候補者については監査役会の同意を得ることとしております。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
社外取締役候補者および社外監査役候補者の選解任・指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会招集ご通知や有価証券報告書等で開示しております。詳細は、当社ホームページをご覧ください。なお、執行役員を解任すべき事情が生じた場合には、適時開示資料などにその理由を記載します。
「株主総会関連資料」
https://www.systena.co.jp/ir/library/general_meeting.html
「有価証券報告書・半期報告書」
https://www.systena.co.jp/ir/library/securities.html
(6)資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するために、資本収益性を意識した経営が重要であると考えています。人的資本への投資や事業ポートフォリオの変革等の取り組みを推進することで、経営資源の適切な配分を実現していきます。また、成長性・資本収益性・財務健全性の3つのバランスをとり、バランスシートの最適化を実現することで、中長期的な企業価値の向上を目指します。
【原則4-10 .任意の仕組みの活用】
【補充原則4-10①任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置】
当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。詳細は当報告書「Ⅱ-1機関構成・組織運営等に係る事項任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」の補足説明に記載のとおりです。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価、その結果の概要】
当社の取締役会の出席メンバーは15名で構成され、うち8名が社外取締役または社外監査役であり、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。取締役会の実効性についての分析・評価を行うにあたり、「取締役会評価のためのアンケート」を用いて、取締役および監査役全員による取締役会の構成及び運営について自己評価を実施するとともに、社外取締役および社外監査役による社外役員ミーティングでこのアンケート分析結果に対する討議を行いました。
アンケートによる自己評価の分析結果および社外役員ミーティングでの討議の結果、当社の取締役会は役員それぞれの知識、経験等を活かし中長期的視点からの継続的成長と株主価値向上に資する議論がなされており、経営の監督に十分な議論が行われていることが確認できましたので、これをもって当社取締役会の実効性は確保されているものと評価いたしました。
当社は原則として、取締役および監査役による自己評価を参考にしつつ、取締役会全体の実効性についての分析・評価を毎年実施し、実効性を維持するとともに効果的な議論がなされるよう更なる改善を進めてまいります。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するために、ディスクロージャーポリシーを定め、開示しております。詳細は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
「ディスクロージャーポリシー」
https://www.systena.co.jp/ir/management/disclosure.html
また、そのための体制整備・取組については、本報告書「III 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の「2.IRに関する活動状況」をご参照ください。
本レポートは、情報提供を目的としたものであり、投資活動を勧誘又は誘引を意図するものではなく、投資等についてのいかなる助言をも提供するものではありません。また、本レポートに掲載された情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、当社は、本レポートに掲載されている情報又は見解の正確性、完全性又は妥当性について保証するものではなく、また、本レポート及び本レポートから得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切についても責任を負うものではありません。本レポートに関する一切の権利は、当社に帰属します。なお、本レポートの内容等につきましては今後予告無く変更される場合があります。投資にあたっての決定は、ご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。 Copyright(C) Investment Bridge Co.,Ltd. All Rights Reserved. |
ブリッジレポート(システナ:2317)のバックナンバー及びブリッジサロン(IRセミナー)の内容は、www.bridge-salon.jp/ でご覧になれます。
 | 同社の適時開示情報の他、レポート発行時にメールでお知らせいたします。 |
 | ブリッジレポートが掲載されているブリッジサロンに会員登録頂くと、株式投資に役立つ様々な便利機能をご利用いただけます。 |
 | 投資家向けIRセミナー「ブリッジサロン」にお越しいただくと、様々な企業トップに出逢うことができます。 |